

弁理士となって実務を覚えたのはシチズン時計株式会社を辞めて転職した特許事務所です。ここで5年間所長参謀として経営の実践をした後、事務所を円満退職し、独立することになりました。33歳、娘2人のときです(1978年)。弁理士の業界では、特許庁がある虎ノ門近辺が事務所のメッカでしたが、私は新宿に馴染みがあったので、伊勢丹の少し四谷寄りの本当に小さな部屋を借り、1人で看板を上げました。5月1日が独立開業記念日ですが、身内数人でささやかなお祝いをしたことを覚えております。
開業当初の数ヶ月は、預金通帳の額がどんどん減っていき、妻は今でも当時どうなることかと不安で一杯だったと話します。尤も私は、最初からある程度の仕事を確保しておりましたので、その成果が入金に繋がるまでの一時的な時間遅れに過ぎないと、全く心配しておりませんでした。事実、預金が底をつく前に入金が始まり、それ以降、現在迄一日として仕事が無かったことはありません。
開業当初は、何しろ働き手が1人ですから、生産、工程管理、営業、宣伝まで全てこなし、それはそれで楽しい毎日ではありました。ただ、何しろ一人ぼっちなので、話す相手がいないというのは結構寂しいもので、当時昼休みになると伊勢丹まで出かけて行って、いらない買い物をしたりしておりました。
そうこうする内に、それまでの仕事の繋がりから若干顧客が増え出し、また年来の友人の勧めもあって、新宿の西口に事務所を転居致しました。
そして、創業2年目から人を少しずつ入れるようにし、事務員として1人から2人と、そして仕事の手伝いとして若い技術者を少しずつ入れて、教育をするように致しました。
技術者ではありませんが、今まで私の影としてYKIを支えてくれたのが、故人と成りました、総務・人事の白倉敏行さんです。白倉さん始め、本当にたくさんの人達に支えて頂きました。
創業から15年の間、ほぼ新宿駅周辺に三箇所オフィスを借り替えながら仕事をし、所員も約50名程度まで増員することが出来ました。この間に気をつけたことは、いつも現場にいることと、お金の使い方でした。現場主義は、どんな職種も同じだと思いますが、最も大事な事だと思っております。またお金を稼ぐことは、結局は如何に誠実に仕事をしたかという結果に過ぎませんが、お金の使い方は、一つ誤ると全くどぶに捨てるようなものだったり、さらに逆効果にもなり兼ねない危うさがあります。
また、仕事をしていれば失敗が付き物です。このときに、どのように対処するかが問題となります。私の場合、早くそして正直に、が常にモットーであり、それを実践してきました。一旦失敗が起きてしまった以上、担当者には一切その責を問わず、私が全て処理する方針を貫きました。
平成5年(1993年)は、私にとって忘れられない年となりました。弁理士会の副会長に就任したのです。この一年間は、殆ど事務所の仕事をすることが出来ませんでした。特許庁との折衝、会員に対する指示、数多の委員会の統括など誠に多忙な毎日でした。当時の特許庁長官は麻生渡氏であり、その後福岡県知事そして全国知事会長と成りました。当時の縁によって、現在に至っても親しくさせて頂いております。このときの副会長の役職により、沢山の人と知合いになれ、またその交誼を現在も続けることが出来、私の人生を豊かなものにしてくれたと思っております。
また、副会長の職務と平行して、自社ビルの建設を推進しておりました。通常は、賃貸オフィスにて仕事をするわけでありますが、東京の賃貸料とりわけ保証金がとても高く、いっそのこと自社ビルを建設して借金返済すれば家賃とさほど変わらない、との考えから、自社ビル建設を模索したのです。
結果的に、山手線内では金額的に折り合わず、順次遠ざかる内に、吉祥寺に物件を見つけたのであります。もともと私は吉祥寺育ちで地の理もありましたので、比較的簡単にここに決めることができました。一年間の副会長の職も無事終わり、1994年の4月に新宿の賃貸オフィスを引き払って移転して参りました。
自社ビル建設には賛否両論がありますが、私の場合、結果的には成功したのではないかと思います。まず、銀行或いは税制からみて、自社ビルは大きな担保価値を持っており、また仮に土地の値下がり等があった場合も、税制上の処置が結構きめ細かくカバーしてくれます。
アジア弁理士協会と申しましても、一般には殆ど馴染みがございません。要するに、アジア各国の弁理士さんの集まりというもので、結構業界で認知された国際団体です。
私は、1994年からこの会に関わりを持ち、爾来アジア各国にて毎年行なわれる国際会議には必ず参加をして参りました。お陰様で、訪問国も30ケ国を超え、それなりの経験も積むことが出来ました。このAPAAは国際組織の中では珍しくも日本が主導的立場を持つ国際組織でありまして、現在でも、日本がリードし大きな顔のできる国際会議となっております。これも、日本の経済・産業の規模、影響力そして特許の出願大国であるお陰でございます。私は、APAAの国際会議の宴会司会から初め、その後、理事、会計、上席副会長、筆頭上席副会長を経て、2009年香港で行なわれた総会においてAPAA会長に推されました。会長任期は3年間で、この間、済州島、マニラの理事会を経て、チェンマイの総会で退任致しました。
2002年には、私事ではありますがもうひとつの慶事がありました。弁理士会での副会長を初めとする種々の役職に従事したことを奇貨として、当時の内閣総理大臣小泉純一郎氏より黄綬褒章を頂くことが出来ました。これも、ひとえに事務所の業務をひとつひとつ誠実に処理してくれる所員の努力の賜と感謝しております。
小泉純一郎首相は、知的財産全体に対しても知財立国という大きな足跡を残しました。2003年、知的財産戦略本部が発足し、知的財産推進計画が毎年更新され、知財はついに我が国の重要政策の筆頭に挙げられるようになりました。
しかしながら、このことは個別事務所の経営に関していえば、必ずしも豊かにしたとはいえません。
40年前には、日陰の花として路地の隅でひそやかに咲いていたのが、いまや閣議のテーマとなり、各企業も必死で知財競争に走り出したのです。
この流れは、知財にとって大きな期待をかけられるという名誉な場を与えてくれましたが、反面、出願人企業からの厳しい品質要求と、企業内知財担当者が特許事務所の競争相手になる、という新たな要求を弁理士に突きつけました。
また、2001年に本格的に始まった司法制度改革は弁理士の増員も求め、2002年には約5,000人であった弁理士数は、2013年には10,000人を超えるまで増加し、弁理士間の競争に拍車を掛けたのです。
更に、国内特許出願件数は、2005年に約43万件のピークを迎えた後、減少に転じ、2008年のリーマンショックもあり、約35万件にまで減少し、以降微減傾向を続けております。
このように、現在の特許業界は、競争の激化と出願件数の減少という二重苦を受け、今までにない厳しい試練の時代に突入したといえるでしょう。
YKI国際特許事務所は、この新しい時代の流れに対応すべく、法人化をすすめ、所長を代替わりし、また取締役社員を広く開放し、顧客の求めに応じられる体制作りを行いました。
その目的とするところは、内外の顧客に、高付加価値の知財権を供給可能な創作性の高い業務の提供であり、量を追うことなく、ひとつずつ高品質の知財製品を地道に供給する知財専門店を目指すことにあります。











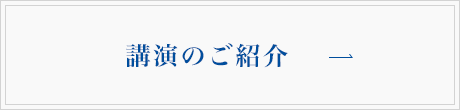
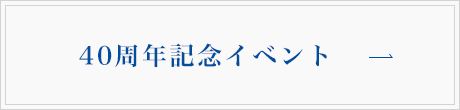
私が、YKIに入ったのは、昭和61(1986)年10月です。所員はそのときの所長(吉田会長)、私も入れて13人でした。案件の期限管理には、沖電気のタイムリーという表計算ソフトを利用していました。8インチのディスクからシステムを読み込むコンピュータを使用していましたが、コンピュータで管理していること自体が進んでいるという印象でした。
また、そのころ明細書作成は、基本ディクテーションで、事務の人が「トスワード」というワープロでテープを聞きながら入力していました。これも、ずいぶん進んでいると感じました。私は、前職で、ワープロを使っていたので、「トスワード(8インチディスク)」を用意してもらい、基本自分で入力しました。
その後、文書作成は、パソコンのワープロソフトに変わり、ワープロ専用機はなくなりました。
私は、YKIに入ったときは弁理士ではありませんでした。前職は、会社の特許部であり弁理士試験も受けたことはあったのですが、一夜漬けなどで試験を受けており、難しさなどはあまりわかっていませんでした。YKIに入った後、弁理士試験勉強のゼミに入り、試験勉強を始め、結構勉強しました。ゼミは、土曜日の午後2時ごろから8時ごろと結構ハードでした。条文を覚えなければならず、ゼミの行帰りには工業所有権法令集を持って読んでいました。ゼミに通っているときに、駅で浮浪者に金をせびられ500円くらいあげたら、「ありがとうございます。聖書を持っている人なので、くれると思った。」などといわれたこともありました。
昭和63(1988)年には弁理士試験に合格し、弁理士登録しました。私が勉強をしている頃、小学生の息子(小6)も中学受験で勉強をしており、作文で「お父さんは、弁理士の勉強をしています」と書いたところ、先生に「お父さんは、弁護士の勉強をしています」と赤字に直されていたのを思い出します。「弁理士」という職業は、いまよりもマイナーだったと思います。
その後、所員数も45名程度となり、平成6(1994)年に吉祥寺に移転しました。移転後も、順調に仕事は増え、現在は第2オフィス、大阪オフィスを開所し、トータルの人員は80名を超える規模になっています。
平成26(2014)年より、吉田会長に代わり、私が所長になりました。比較的、誰でも何でもいえる自由な気風も、YKI吉田会長がつくってくれたもので、私は大好きです。このような気風もYKIでの仕事の質の向上につながっていると思っています。
近年は、多くのクライアントが、明細書の品質評価を行っていますが、YKIは多くのクライアントから高い評価を受けています。吉田会長が、多くの明細書の事前チェックを行ったり、評価の悪かったものについては、会議でみんなが検討し改善しているからだと思います。何事も、日々の地道な努力が大事であり、これからも各人が研鑽しクライアントによいサービスを提供できるように努力することが必要でしょう。
また、クライアントによりよいサービスを提供するためにも、所員のみんなが幸せであることが大切であり、みんなが意見をいって、よりよい事務所にしたいと思っています。
また、YKIでは10件程度の侵害訴訟に補佐人、代理人として関与しました。また、国内出願人の外国出願や国外出願人の日本出願の代理についても、私がYKIに入所した当初からある程度行っており、これらを合わせた仕事量は、現在も全体の半分くらいになっています。
これらの経験、知識を皆で共有することも出願手続きを適切に進めるうえで、重要なことであり、グローバルな視点を持つことも大切です。YKIは、これらの経験を生かしてクライアントによりよいサービスを提供していく所存です。